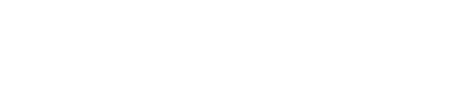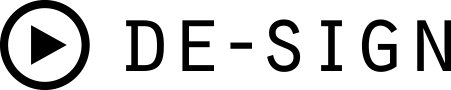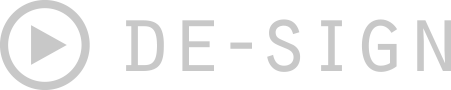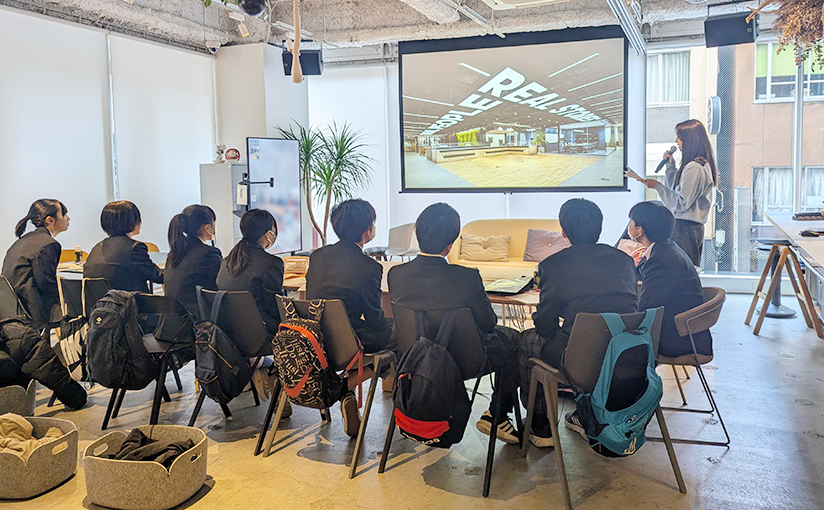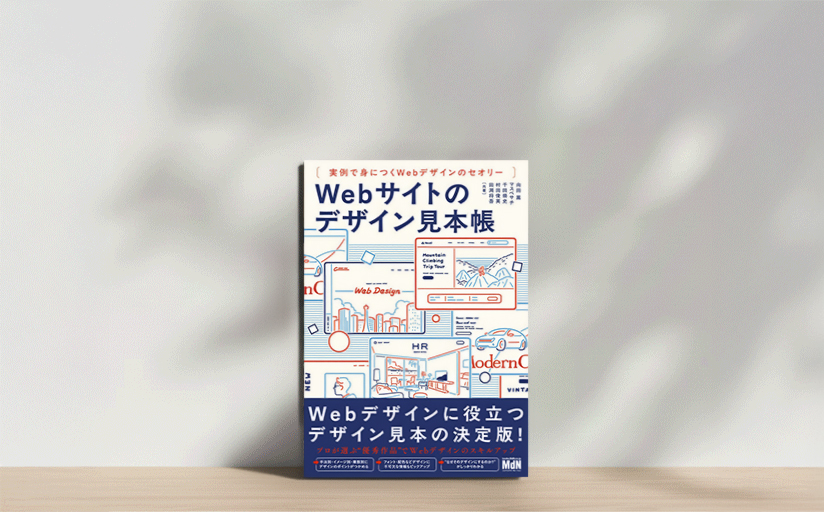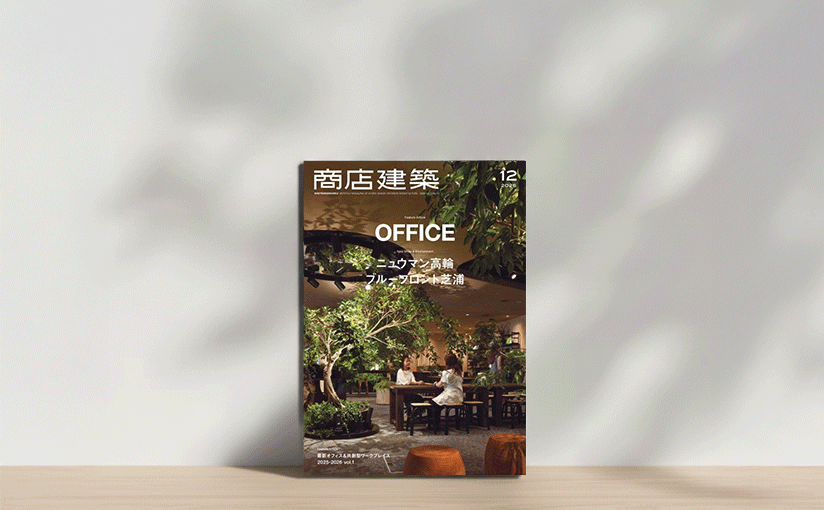12.Feb.2025 COLUMN 消防法は確認済み?オフィス移転で必要なことをご紹介。
オフィスのレイアウトを検討していると、実現したいことやデザインに意識が向いてしまいがちです。しかし、いざという時に従業員の命を守る「消防法」を忘れずに確認しておく必要があります。消防法とはどんなものか、また、具体的にオフィスの構築時に考慮しなければいけない消防法の規定はどんなものがあるのか、ご紹介します。
※最新情報は、各管轄機関の公式サイトをご確認ください。手続きの期限や管轄先の変更などは、法改正や地域差がある場合があります。

消防法の中身とその中でもオフィス移転の際に行うべきことを確認。
消防法とは?
消防法とは、火災予防や災害発生時の被害軽減などに関する法律です。下記の目的に沿って制定されています。
第一章 総則
第一条この法律は、火災を予防し、警戒し及び鎮圧し、国民の生命、身体及び財産を火災から保護するとともに、火災又は地震等の災害による被害を軽減するほか、災害等による傷病者の搬送を適切に行い、もつて安寧秩序を保持し、社会公共の福祉の増進に資することを目的とする。
>引用元:消防法 | e-Gov法令検索
消防法は、すべての建築物に適用され、管理者に消防用設備の設置と定期点検を義務づけています。 消防法を遵守することは、単なる法的義務を超え、従業員の安全・生命を守るために必ず守らなければいけないものです。消防法に従わない場合は、それぞれの罰則が適用される場合があります。
オフィス移転の際に行うべきことを、3つにまとめて解説。
消防法の中でもオフィスの移転をする際に考慮することは下記3つのカテゴリーにまとめられます。それぞれ、実際に何を行うべきなのか解説します。
- A:オフィスの内装・レイアウトで考慮すべきこと
- B:必要な手続き
- C:必要な点検・訓練
A:オフィスの内装・レイアウトで考慮すべきことは5つ。
オフィスの内装・レイアウトを検討する際には、主に下記5つの観点から消防法に違反しないよう考慮してレイアウトを決めましょう。
①内装制限
火災による建物への被害を最小限に抑え、人命を守るために定められている内装施工の規定です。内装制限は、「建築基準法」と「消防法」の2つの法律によって定められています。これらが設けられている目的は、オフィスや商業施設などの利用者を火災の被害から守るためです。
消防法で「防炎防火対象物等の建築物」と定められた建物は内装制限に該当します。
建築基準法による内装制限の場合、「床面からの高さが1.2メートル以内(腰壁)」は、内装の仕上げ材に難燃以上の防火材料を使用しなければいけない範囲から除かれていました。 しかし、消防法では、腰壁であっても難燃以上の防火材料を使用することが定められています。消防法では壁全面が内装制限の対象となる点に注意しましょう。しかし、内装制限には緩和策もありますので、設計者とよく相談して内装を決めていくことをお勧めします。
②避難経路の確保
避難経路に関しても、「建築基準法」と「消防法」の2つの法律によって定められています。避難経路(通路)幅は最低でも1.2mは必要で、用途や居室の有無によって最大2.3mもの幅員を設けなければなりませんので、こちらも設計者とよく確認して決めていくことをお勧めします。消防法上では、消防法第8条の2の4〔避難上必要な施設等の管理〕で避難障害になる物品の除去等についてのみ規定されていますが、幅員についても火災予防条例で細かい数字が規定されています。通路幅の規定を含め、建築基準法とあわせて確認しながら設置しましょう。
③個室ブース
オフィスに個室ブースを取り入れる際に、消防法の制限に従おうとすると、消防用設備を設置しなければなりません。例えば、ブース内での火災を想定した煙感知器やスプリンクラーヘッドの設置、また火災発生時の警報音や非常放送の音がブース内でも聞こえるようにするスピーカーなどの設置が必要となります。ですが、天井及び壁により囲われたブースで、防火対象物の床や壁に固定(工具等で簡単に取り外すことができるものを除く)されておらず、人が出入りして利用するものについては、一定の条件を満たすと、煙感知器やスプリンクラーの設置が免除される特例申請があります。その条件は消防庁に確認して設置を進めるのが望ましいです。
④防炎物品
オフィスでは防炎性能を持つカーテンやカーペットなどの使用が義務付けられています。オフィスは不特定多数の人が出入りする施設・建築物に該当するため、「防災物品」を使用しなければなりません。カーテン、緞帳、ブラインド、合板、カーペットなど以下のような物品は、防炎性能を備えた製品を使用する必要があります。
- ●カーテン
- ●カーペット
- ●パーティション
- ●椅子やソファの布地
- ●壁面装飾布
- ●展示用幕・のれん など
⑤消防用設備の設置
大きく分けて3つの要件があります。オフィスの規模によっては、消防設備の設置が義務付けられます。
- ●消防関連設備
- ●消火設備(消火器具、屋内消火栓設備、スプリンクラー設備)
- ●警報設備(自動火災報知設備)
- ●避難設備(避難器具、誘導灯)
- ●消防用水
- ●消火活動上必要な施設
(連結送水管、排煙設備、非常コンセント設備etc.)

生成AIによる画像
B:消防法関連の必要な手続きは5つ。
オフィス移転時には、以下の手続きを適切に行う必要があります。
①防火対象物工事等計画届出書
内容:建物や建物の一部を工事する場合に必要な届出。
期限:造作工事(室内レイアウト工事)開始日の7日前
届出先:防火対象物を管轄する消防署
②防火対象物使用開始届出書
内容:建物や建物の一部をこれから使用しようとする方が届出するもの。
期限:使用を始める7日前
届出先:管轄消防署
③防火管理者選任(解任)届出書
内容:対象の事業所に50人以上の従業員が在籍している場合には防火・防災管理者の選任と前のオフィスへの解任届出が必要。また、防火・防災管理者に選任された者は、消防計画を作成し、届け出る義務がある。消防計画には、防火対策、避難経路の確保、消火設備の設置、避難訓練、教育などを記載する必要がある。
期限:オフィス移転日まで
届出先:各管轄消防署(元オフィスに解任届出書・新オフィスに選任届出書)防火・防災管理者を選任(解任)する場合に管轄の消防署に提出する届出書。
④消防用設備等設置届出書
内容:建物に消防用設備等を設置したときに必要な届出。また、届出後、原則として消防署の検査を受ける必要がある。
期限:設置後、4日以内
届出先:管轄消防署
⑤避難訓練の実施報告(一定規模以上のオフィスで必要)
内容:大規模建築物等については、防災管理業務の実施が義務付けられ、その実施状況を毎年1回定期的に防災管理点検資格者に点検させ、その結果を消防機関に報告する防災管理点検報告制度。対象となる建築物は、日本消防設備安全センターのサイトが参考になりそうです。対応するのはビル単位になることが多く、主に建物のオーナー等から、その報告書を消防長または消防署長に提出。
期限:移転の有無に関わらず毎年1回定期的に
届出先:管轄消防署
C: 点検・訓練で必要な手続きは2つ。
移転の有無にかかわらず、従業員の安全を守るために下記2つの点検と訓練は大切です。特に移転後は新しい環境になり、従業員は被災時の対応に関する情報がありません。移転後は早めに、災害発生時に設備が正常に機能し、従業員が避難経路や消火器の使用方法を知っている状態にすべきです。点検と訓練を怠ることなく、実施しましょう。
- ●消防点検
消火器、火災報知機、避難誘導灯などの点検を定期的に実施しましょう。
機器点検は6か月に1回、総合保険は1年に1回がおすすめです。
- ●防災訓練
上記B-⑤にも記載した通り年1回の避難訓練や、従業員に避難経路や消火器の使用方法を周知する防災訓練の実施を行いましょう。

生成AIによる画像
補足:消防法と合わせて確認したい建築基準法
建築基準法とは、国民の命を守るために建物に関する最低限の基準を定めた法律のことです。よって内装においても計画・設計する上では、消防法以外に建築基準法も切り離せない関係にあります。消防法だけ守っても建築基準法の規定を満たしていないとオフィスとして成り立たなくなってしまう、ということは避けなければなりません。例えば「A-①内装制限」や、「A-②避難経路の確保」でも述べた通り、どちらの法律も理解する必要があります。そのほかにも下記が合わせて確認しておきたい建築基準法のポイントです。
- ●耐火建築物の基準:オフィスが入居する建物の耐火性能を確認。
- ●避難設備の規定:非常階段や避難ハッチの有無。
- ●使用用途の制限:オフィス用途に適した建物かどうか。
- ●避難距離の基準:直通階段までの避難距離及び2方向避難までの重複距離が、入居フロアの高さ(階数)によって定められた範囲内かどうか。
消防法と建築基準法を正しく理解し、適切な手続きを行うことで、安全かつスムーズなオフィス移転が可能になります。
消防法を見落とさないオフィスレイアウトはディー・サインにお任せ
オフィスの安全確保には、消防法を正しく理解し、適切なレイアウトを設計することが不可欠です。しかし、専門知識が必要なことや煩雑な手続きが多くあり、「社内だけでは細かく確認することは難しい」というお声をよく耳にします。ディー・サインでは消防法の細かいポイントも抑え、常にお客様のプロジェクトを伴走してきました。総合的なオフィス改修・構築のパートナーをお探しの場合は、ぜひお問い合わせください。